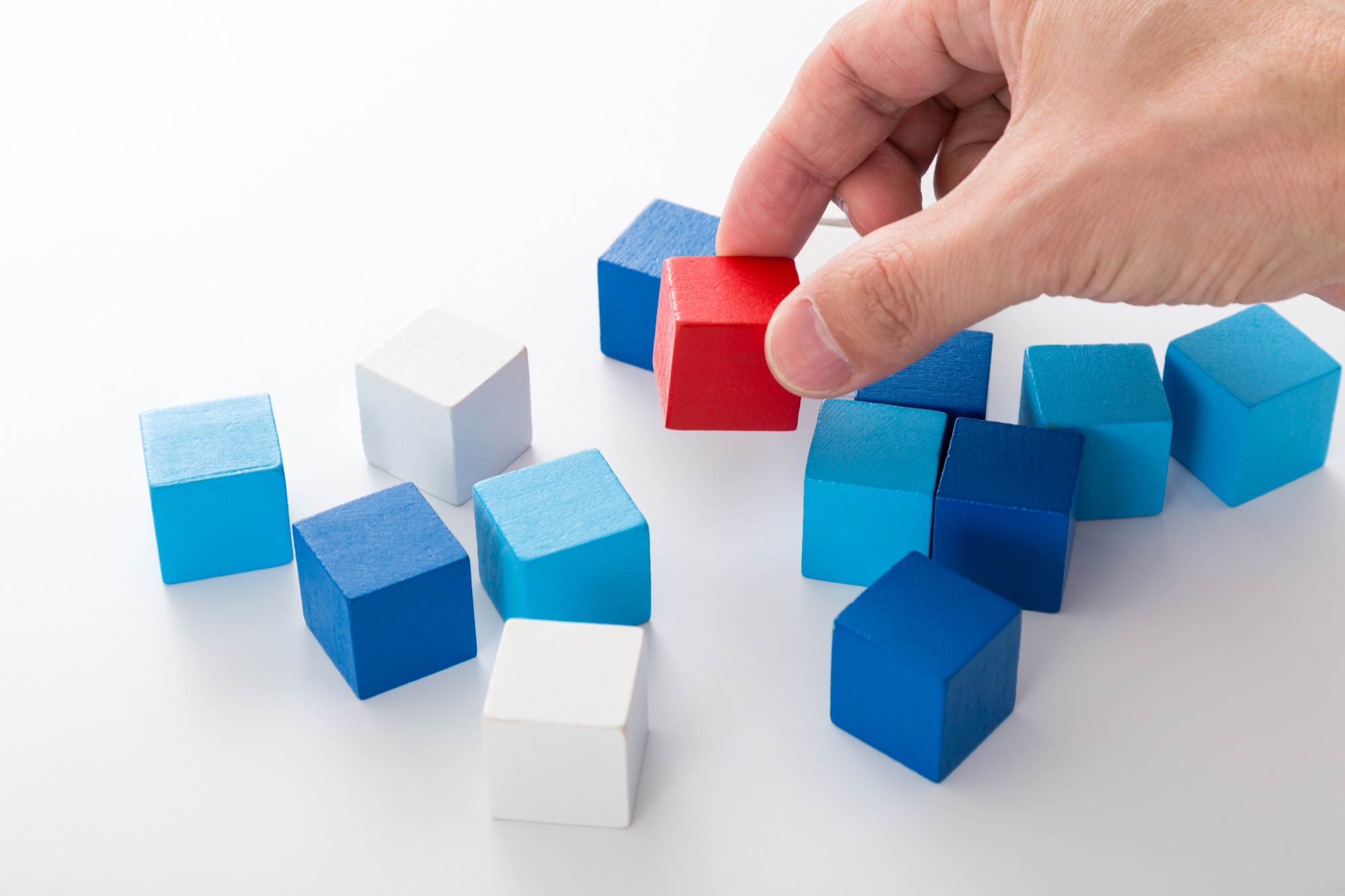IoTやAIの技術の進展により、大型機械の故障予知や異常検知への取り組みが進んでいます。この記事では、具体的にどのような手法で故障予知を行うのか、その際の注意点は何かを解説していきます。
異常検知とは
異常検知とは、計測値を機械学習させることにより異常な状態を検知するための手法です。例えば、通常とは異なる動作や音などは異常検知の対象となります。 異常検知は、機械学習を用いることで、さまざまな場面で応用されており、産業機械の稼働状況や画像による製品異常の検出などにも利用されています。また、異常の有無を検知するだけでなく、現在ではデータ分析を行うことによる故障予測も可能です。
IoTやAIを活用して異常検知するには前提が必要
異常検知にIoTやAIをなどの情報システムの導入を検討している企業、予知保全システムの構築を検討している企業は増加傾向にあります。 しかし、IoTやAIを導入するうえではデータの計測が欠かせません。予知保全システムでは、対象となる設備や機械にセンサーを取り付けることで、状態を把握するためのデータの計測を行います。その後、IoTを使ってデータを収集し、そのデータに関してAIなどで解析を行うことで、故障や不具合を事前に察知することが可能となるためです。
IoTやAIは、現場で計測したデータを有効活用する技術であるため、高精度な計測が求められます。計測したデータの精度が低いと、IoTやAIを導入したとしても期待通りの成果が生み出される可能性は低いでしょう。そのため、IoTやAIの活用を考えるのであれば、高精度なデータの計測が行えることが前提となります。
データが十分に無い場合の異常検知手法
工場機械の異常などは、頻繁に起きる可能性が低いため、過去のデータが十分にない場合もあります。このようにデータが不足している場合に用いられるのが「教師なし学習」です。 教師なし学習とは、AIが与えられたデータから規則性を発見し、学習を行っていく機械学習の手法です。教師なし学習で代表的な手法は、SVDD、PCA、RPCAの3つです。それぞれの手法に関して解説していきます。
SVDD
SVDDは1クラス分類を目的とする教師なしの機械学習法です。1クラス分類は、学習時に少数派クラスのサンプルがほとんど得られない場合に有効です。そのため、SVDDは、異常の実例があまりないデータでもうまく機能します。2つのデータの間のある種の類似度を表す関数であるカーネル関数を使用することにより、「通常」の領域、異常検知においては正常な状態の領域を柔軟にモデル化することが可能です。そのため、機器予後診断や健康管理、詐欺の識別などに用いられることもあります。
PCA
PCAは主成分分析と呼ばれるデータ解析手法の一つです。PCAでは、データの持つ情報をできる限り損なわず、データ全体の雰囲気を可視化することが可能です。PCAによる異常検知は、正常なデータの領域(通常状態)を規定して、それを逸脱するデータを異常と判定します。異常検知の他にも、パターン認識などさまざまな場面に適用できます。
RPCA
RPCAは堅牢な主成分分析と呼ばれるデータ解析手法の一つです。PCAの統計的基準を修正したものであり、他のデータと大きくかけ離れたデータに対しても適切に機能するのが特徴です。用途としては、異常検知・画像処理などに使用されています。
異常検知・故障予知を行うにあたっての注意点
異常検知・故障予知を行う場合、システムへの理解が必要です。IoTやAIを活用した異常検知・故障予知では、タイムラグを考慮した設計が必要となり、経年による変化も考慮しつつ、モデルの更新サイクルを定めていかなければなりません。 教師あり学習の場合、異常を検知できる確率が最初からわかっているため、異常かどうか判断しやすいという特徴があります。それに対して、教師なし学習の場合は、異常値を検出できるもののそれが異常かどうか判断するのに別の判断基準が必要です。そのため、類似度などの指標をもとに、しきい値を正しく設定し、異常を判断しなければいけません。
AIの機械学習に教師なし学習を用いる場合、正解の定義が定められていないため、手法ごとの特徴を理解したうえで、複数の手法で判断することによって良い結果を得ることが可能です。また、データ計測の質にも注意が必要です。工場内の機械や部品などに対して異常検知・故障予知を行う場合は、現場の状況が正確に分かるような高精度の計測が大切です。

AIを活用した故障の予知方法「稼働監視」
稼働監視は、製品のIoT化を行うことで稼働状況を可視化する方法です。製品のIoT化を行うことで、製品からデータ取得が容易になり、機器が動作しているかを把握できます。また、製品の制御情報を収集することでどういった状態で稼働しているのかも確認することができます。 稼働監視に必要な要素は、製品情報のセンシングを行い、通信機能を利用し、その情報を収集することです。こうした情報を分析しつつ、AI関連技術を活用することで、過去や現在の状況だけでなく、未来の状況を予測して予兆保全を行います。
機械や消耗品の経年劣化などは避けることができないため、企業としては予兆保全を実施したいと考えるでしょう。しかし、予兆保全は、故障予測を正確に行う必要があるため、稼働監視から予兆保全を行うのは簡単ではありません。故障に対して、どういったセンシングデータが正しい予兆を捉えているのかを把握する必要があり、重要な指標となるデータを得るためには時間がかかります。また、時間軸や粒度も考慮しなければいけません。
また、正確な予知を行うためには、故障と相関性のある指標を複数組み合わせる必要があるため、すぐに期待通りの成果が出るとは限りません。さらに、故障予知を進めるうえで、機械などの故障はそう頻繁に起きないため、故障データが集まりにくく、AIに有効な学習を実現することが難しくなっています。
そんな状況でも、自社製品の徹底的な試験を行っているメーカーでは、自社製品と故障との相関性があるポイントを把握している場合も少なくありません。そのため、予兆保全を実際に行っている企業があり、現在では予兆保全をサービスとして提供する会社も徐々に現れはじめています。稼働監視から予兆保全を行うことで、競争力を高めつつ、機械や部品などの突発的な故障を防ぐことが可能となるでしょう。